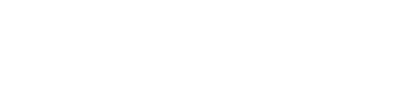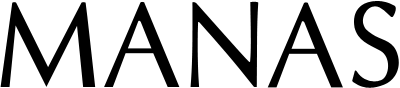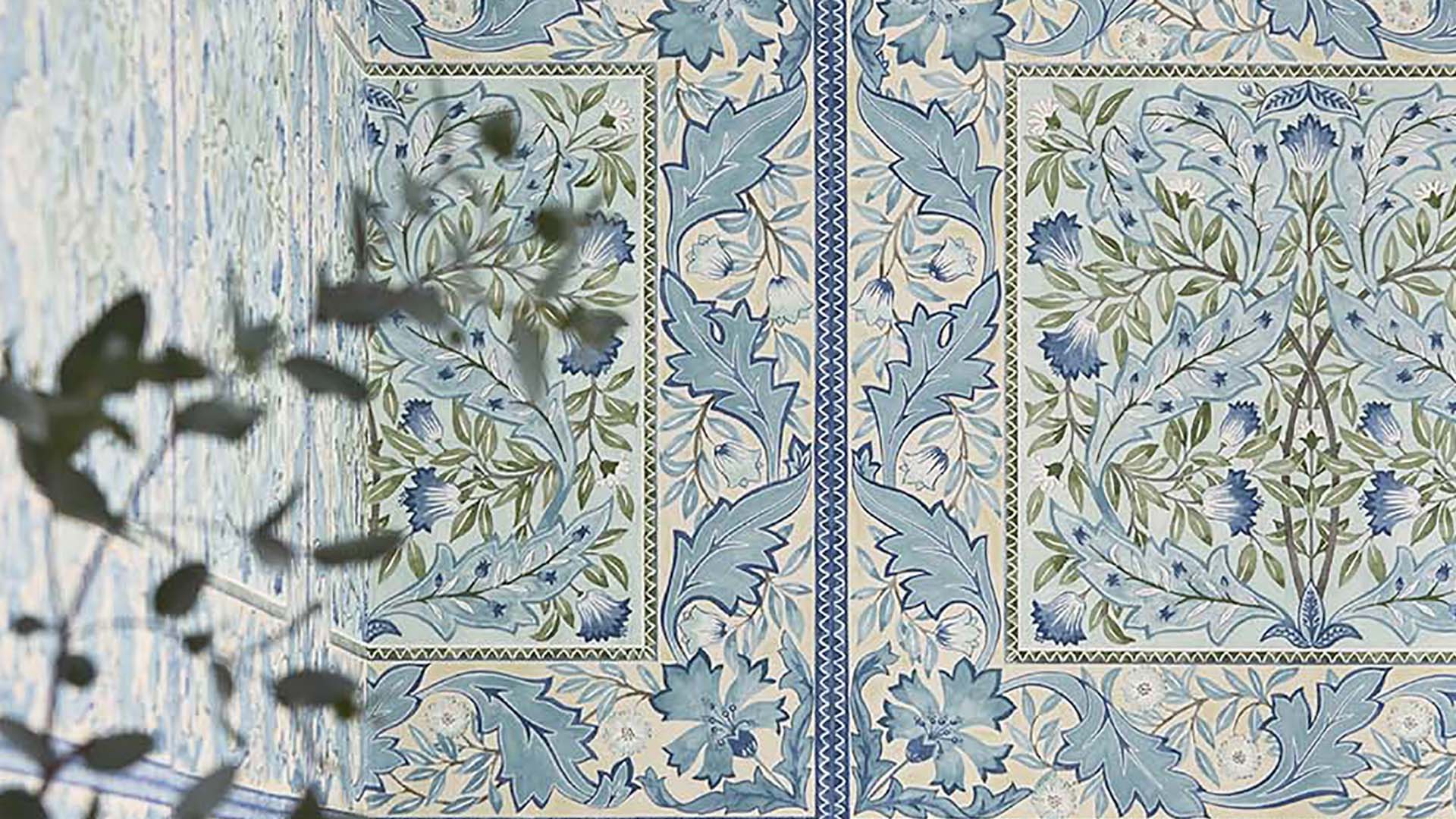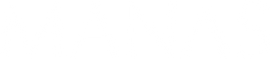Best of Best Practice
共有ポイント
- 未来に種を撒く、MANASベストプラクティスの軌跡
発表者
営業企画部 牧野 蘭(まきの らん)
営業企画部 三谷 沙也佳(みたに さやか)
事例を通してノウハウの共有と営業プロセスの可視化を目指す「ベストプラクティス」。MANASが初めて取り組んだ「ベストプラクティス(以下、BP)」プロジェクトは、成功事例や効果的な手法を共有し、営業プロセスを見える化することを目的としています。これは、他者の経験を学びに変え、自身のスキルや成長に役立てる手法で、すでに多くの企業でも活用されています。
今回、1年間にわたりこの取り組みを推進してきた牧野さんと三谷さんにインタビューを実施。試行錯誤を重ねながら続けたこの活動を、どのように企業文化として根付かせていくか、その苦労や工夫について語っていただきました。新しいチャレンジを社内に浸透させるまでのプロセスに迫ります。
― ひとつの記事を投稿するまでのプロセスを教えてください。
1. 部門長会議にてタネ集め
部門長会議にて各部門長から、部内のベストプラクティスを出してもらいました。(担当:山上さん)
2. BPメンバーにて選定
部門長会議で出てきたタネから配信の準備に入るものを選定します。
3. インタビューシートの送付
インタビュイーに配信予定の約1か月前までにシートを送付し、記入してもらいました。
4. インタビュー
事前に提出いただいたシートをもとにインタビューをします。共有ポイントは何かを掴むために、もっと話を聞いてみたいと感じた部分や、詳しく伺いたい部分を確認したうえで対面またはオンラインで実施しました。
5. 文字起こし、記事作成
インタビューにて伺った内容をもとに原稿を作成。
6. 校正(BPメンバー)
原稿の内容、構成の確認、文字校正を山上さん、林さんにしていただきました。
7. 校正(インタビュイー)
原稿に資料や画像を入れ込んだものをWEBページに起こし、インタビュイーの方に内容の事実確認や伝えたい想い(ポイント)に差異がないかを確認していただきました。
8. 配信
月に3-4回のBP配信スケジュールを組み、情報共有のサイクルを定着させることで、社員への早期浸透とインプットの習慣化を目指しました。
― 今回の取り組みを進める中で最初にぶつかった壁はどんな内容でしたか?また取り組み前はどんな状態でしたか?
牧野)(以下、牧)最初に感じた壁は、共有ポイントの設定でした。営業メンバーにインタビューをする際、ジョブローテーションでおおまかな動きは把握していたものの、具体的にどのように営業や販促活動をしているのかまでは見えていませんでした。そのため、一連の活動の流れの中で初めて知ることが多すぎて、「この人がやったことのどこがポイントなのか」を見つけることができず、結局、記事にしても伝えたいことが曖昧になってしまい、再インタビューすることもありました。もっとインタビュイー自身も気づいていないポイントを引き出せるようになりたいと思いましたし、自分の語彙力や表現力の乏しさにも驚きましたね(笑)。
三谷)(以下、三)私も同じで、インタビューでどこを掘り下げればいいのか分からず苦労しました。さらに、文章の構成やまとめ方にも悩んで、インタビューから記事にするまで、本当に試行錯誤の連続でした。
― その壁をどうやって乗り越えてきましたか?
牧)定例ミーティングで山上さんや林さんと、いま私たちが感じている課題を共有し、解決策を話し合う中で、「共有ポイント」を明確にする方法を見つけました。具体的には、インタビュー前にシートを確認し、不明な環境的背景や商品情報を予備知識としてインプットします。さらに、BPメンバー間で深堀りするポイントをすり合わせることで、事前準備が整い、スムーズな進行ができるように。
また、「共有ポイント」を「自分がこの人のここがすごい」と感じた部分と捉え直したことで、記事の軸も掴みやすくなりました。その結果、記事作成の精度とスピードが向上し、情報の整理や表現にも自信がついたと感じています。
三)インタビュー前にシートを確認し、疑問点を事前に洗い出すことで、BPミーティングの場で山上さんや林さんと壁打ちを行い、インタビューの方向性を明確にすることができました。記事作成では、共有ポイントを整理し、起承転結を意識することで、記事全体の構成を考えやすくなりました。インタビュー前に各質問で押さえたい内容を整理できるようになったため、以前よりも読者が読みやすく、まとまりのある記事になったと実感しています。
また、文章表現が苦手だったことから、Googleの「Gemini」を活用してアイデアや表現の幅を広げ、効率化を図りました。ただし、AIで生成された文章をそのまま使用するのではなく、必ず内容を確認し、より適切な言い回しに修正することが重要です。AIの力を借りながらも、自分の言葉で最終チェックを徹底することで、読者にしっかりと伝わる記事作成に努めました。
インタビューのようす
― インタビューしてきた中で印象に残っていることや、自身も取り入れたノウハウがあればお聞かせください。
牧)印象に残っているのは、御所さん、田邊さん、水野さんなど、長年MANASで活躍されている方々のインタビューです。普段の業務では聞けない深い話を直接伺えたのは、とても貴重で刺激的な経験でした。特に「インテリアを底上げし、美しい空間を提案する」という田邊さんの想い、「お客様と泥臭く信頼関係を築く」という水野さんの姿勢、御所さんの「自分はお客様の手助けに過ぎない」という言葉から、MANASらしい誠実さを感じました。
具体的にノウハウを取り入れた場面はまだ少ないですが、営業メンバーそれぞれの信頼の築き方や考え方を自分の引き出しに入れることができました。今後営業の現場に立つ時には、「お客様ではなく、一人の人として向き合う」という意識を日常的に持ち、営業としてというより、マナトレーディングの牧野として向き合う、自分自身のスタイルで提案していきたいと考えています。
三)特に印象に残っているのは、八尾さんから学んだ「スケジュールはゴールから逆算して考える」という方法です。以前は先の予定を立てるのが苦手でしたが、締切から逆算することで必要なステップが明確になり、計画倒れを防ぐことができるようになりました。目標達成までの道のりが整理されることで、モチベーションアップにもつながっています。
また、高山さんからは「提案時には最低でも2パターン用意する」ことの重要性を学びました。ひとつの案に固執せず、相手の選択や反応を見ることで潜在ニーズを探るという姿勢は、仕事の幅を広げるうえで大切だと実感しています。学生時代は自分の個性を前面に出すことが評価につながりましたが、社会では「相手のニーズに合った提案をする」ことが求められる。そのギャップを実感しながらも、より良い提案ができるよう努めていきたいと思います。このことは「家具フェアで使用するラグの縮尺図面」や「広島のSALE案内はがき」でより実感することができました。
― 今回の取り組みを始めたころといまを比べると、何が一番変化したと思いますか。
牧)一番変わったのは「発信する側としての責任感」が芽生えたことだと思います。ベストプラクティスは発表者本人が記事を書くわけではなく、私たちが代わりに文章をまとめ、発信する立場なので、言葉選びには特に気を遣うようになりました。読み手には、あくまで発表者の言葉として届くわけで、たとえ私たちが書いた内容でも、そのままその人の印象で伝わってしまいます。
最初のころは原稿を書くことに必死で、「とりあえずまとめる」という状態でしたが、山上さんや林さん、そして高山さんとの打ち合わせを重ね、「この想いを伝えるにはどの言葉が最適か」を意識するようになりました。検索履歴も「○○とは」「○○ 類義語」で埋まってしまい、日本語の難しさや奥深さを実感しましたね。
特に高山さんとは「どう伝えればいいのか」を何度も話し合ったことで、言葉に対する責任と重みを学びました。そうした過程を経て、文章を作ることが単なる作業ではなく「想いを形にする仕事」だと捉えられるようになり、大きな成長を感じています。
三)BPに取り組んで一番変化したのは、「人とのつながり」と「最後までやり遂げる責任感」が強くなったことです。私は元々人見知りなので、BPがなければ他部署の方とここまで深く関わる機会はなかったと思います。特に営業所の皆さんに自分の存在を知っていただき、気軽に声をかけてもらえるようになったことは、自分にとって大きな前進でした。
また、文章作成に対しては苦手意識が強く、記事を書くたびに胃が痛くなるような状況でしたが、夜遅くまで作業していると先輩方が声をかけてくれたり、励ましてくれたりして、その気遣いが支えになりました。自分は感受性が豊かで、人の感情を汲み取りやすいところがあると感じています。だからこそ、インタビューを受けてくださった皆さんの想いを、その熱量のまま届けたいという気持ちが強かったです。
記事を書くことは簡単ではありませんでしたが、「伝えたい」という気持ちが、最後までやり遂げる原動力になりました。そしてその過程で「発信することへの使命感」も自然と芽生えたように思います。
― インタビューをしていく中で、MANASに対するイメージが変わったところはありますか?
牧)MANASに対するイメージが「変わった」というより、「より強く実感した」ことが大きかったです。それは「社員の皆さんが本当にMANASの商材を好きである」という点です。どなたにインタビューをしても、私たちのブランドや商品に対する誇りや愛情が伝わってきました。
「MANASの商材なら絶対にお客様の役に立てる!」と自信を持って話される方が多く、その熱量がとにかく印象的でした。田邊さんが「インテリアを底上げするため、美しい空間を提案したい」と語っていたり、水野さんが「いい意味で泥臭く、信頼関係を作る」と話されていたり、御所さんが「自分ができるのは手助けだけ」と謙虚に語っていたり。それぞれにMANASらしさがあり、共通して「この商材が好き」「誇りを持っている」ことが伝わってきました。そんな先輩方と関わる中で、私も「お客様に向き合う姿勢」をより大切にしていきたいと思うようになりました。
三)正直に言うと無いです。それはMANASに対するイメージが大きく変わったというより、「働いている皆さんの人柄」に改めて感動した、という感覚に近いからです。インタビューでは、皆さん本当に忙しい中にも関わらず、嫌な顔ひとつせず、丁寧に協力してくださいました。その姿にまず感謝の気持ちが強くなりました。
そして、インタビューを通して感じたのは「皆さんが自分の仕事に誇りを持っている」ということです。難しい案件や大変な現場でも、最後まで諦めずやり遂げる。その背景には、MANASの商材やブランドに対する愛情と誇りがあるのだと強く実感しました。普段はユーモアで場を和ませてくれる先輩方も、仕事となれば真剣な表情でプロフェッショナルな仕事をしている姿を見て、私もそうなりたいと感じました。この経験を通して、「仕事への誇りと情熱」を持つことの大切さを学びました。
― ベストプラクティスを通してやりがいを感じた瞬間を教えてください。
牧)やりがいを感じたのは、BPの配信をきっかけに開催した社内イベントに、多くの方が参加してくださったときです。BPの目的は「ノウハウの横展開」と「社内の活性化」ですが、配信中は本当に役立っているのかと不安に感じることもありました。しかし、実際にイベントに参加してくださる方々を見て、「やっていて良かった」と思えました。特に、瀬戸さんからウェーブスタイルの勉強会資料の依頼や、樋口さんからも問い合わせがあった際には、BPの取り組みが社内に浸透していることを実感しました。
『今こそ知りたい!ウェーブカーテン講座』のようす
インタビューを通して得た経験や知識を文章にし、「誰でも読める形で残せた」ことも大きな成果です。数年後、「あの時の記事が役に立った」と言われることがあれば、それは最高の達成感だと思います。何も知らないからこそ持てたフラットな視点で、読み手の立場に立った記事を書けたことも、やりがいに繋がっています。
三)配信したLINEのリアクションが多いときです。(笑) 自分が作成した記事を誰かが読んで反応をくれるというのは、単純ですがすごく嬉しいことで、「配信してよかった!」という気持ちになります。リアクションがあると「役に立った」「楽しんでもらえた」と実感でき、自己肯定感も上がります(笑)。また、配信に協力してくれた方々への感謝の気持ちも湧き、次へのモチベーションにも繋がります。
そして、ルートロンの勉強会を企画・実施したことも印象に残っています。記事を書く中で、「実際に話を聞くだけでなく、リアルな場で共有すべきでは?」と感じ、内山さんや山邉さん、柳田さんの協力を得て勉強会を実施しました。デモ機の準備から進行まで、社内の色々な人が関わってくれて、一体感を感じることができました。参加した営業2部の方々が、実例を交えて活発に意見交換してくれたのも嬉しかったです。「やって良かった」と思える瞬間でした。
『LUTRON勉強会~提案後に必要な知識~』のようす
― 皆へのメッセージをお願いします。
牧)インタビューにご協力いただいた皆さん、嫌な顔ひとつせずに、追加の質問やお願いにも何度も快く応じてくださいました。共同者や推薦者の方々も、親身になって対応してくださり、心から感謝しています。MANASの皆さんに支えてもらったからこそ、書き続けられたと実感しています。小さなことでも感想をいただけると、とても嬉しいです!
三)支えてくださった山上さん、林さんをはじめ、お忙しい中記事作成にご協力くださった皆様、本当にありがとうございました。BPを配信したことで、少しでも会社の力になっていれば幸いです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

(右)
部署名: 営業企画部
氏 名: 牧野 蘭(まきの らん)
入社日: 2023年4月
(左)
部署名: 営業企画部
氏 名: 三谷 沙也佳(みたに さやか)
入社日: 2023年4月
― MANASの入社経緯をお聞かせいただけますか?
牧)フラワーアレンジメントの習い事をきっかけに独自で色彩の勉強をしていたため、その知識を生かせるような会社で働きたいと感じ、就職活動のときに花卉業界とインテリア業界を見ていたところ、MANASに出会いました。会社説明会で実際に社員の皆さまと対面し、雰囲気に惹かれ、ご縁があり入社させていただきました。
三)大学で家政学を学んでいくなかで、人々の暮らしや生活、住まいに興味を持つようになりました。学生時代、コロナ禍でおうち時間が増えたことから、気分転換も兼ねて部屋の模様替えを行ったところ、インテリアがもたらす心の安らぎを実感しました。この経験から、住空間を通して、より生活を豊かにできる仕事に就きたいと思い、インテリア業界を志望しました。説明会で案内してくださった保科さんや、面接をしてくださった洋平さん、山本(将)さん、川井さんの人柄の良さに惹かれ、第一志望だったMANASへ入社させていただくことになりました。
― いまはどんなお仕事を担当されていますか?
牧)販促企画や広報、新たにAIプロジェクトを担当しています。
三)主に販促物やWEB関係を担当しています。
共同者:
営業企画部:山上 紘子
営業企画部:林 聖来